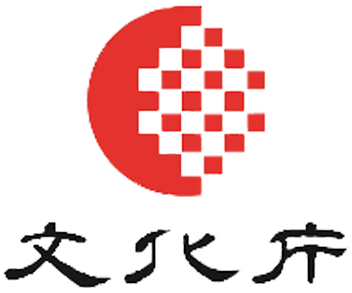南丹地域|亀岡市
 京都市山科区のアトリエにて
京都市山科区のアトリエにて
蓮の花や擬宝珠(ぎぼし)を象った陶磁器のオブジェ。垂直にスッと伸びる端正な佇まいは、仏塔の先端に据えられる相輪(そうりん)を思わせます。仏教的なモチーフを扱いながらも、しかしどこかロココ様式の教会建築のようにも感じられます。東洋的でかつ西洋的、そして伝統的でありながらも現代的。そんな相反する要素を共存させる絶妙なバランス感覚に、西久松さんのアーティストとしての非凡なセンスを感じます。
 個展『化生』(2022)の展示風景。 壁面が《徒花》(2022)、右手前が《常花》(2022)
個展『化生』(2022)の展示風景。 壁面が《徒花》(2022)、右手前が《常花》(2022)
さらにじっくりと観察していくと、どの作品も至るところに非常に手の込んだ技巧が散りばめられていることに驚かされます。
「この部分は色むらが出るように、撥水液を染み込ませた糸を巻いた後に釉薬(ゆうやく)をかけています」、「粘土を小さな穴から押し出して細い糸状にしてから型に押し固めて成形し、さらに青の顔料を染み込ませて表面をスポンジで磨くとこういった表現になります」、「これは顔料を混ぜた粘土を一度乾燥させてから砕いたもので、素地の部分とは釉薬の色の透け方が違っています」
高い技量の求められる細工、珍しい技法による表現、真鍮やスワロフスキー、パール、組紐など異素材との組み合わせ等々、ディティールにこだわって作られているのです。
 左から《冥華》(2021)、《阿迦》(2021)、《濁世に在る花》(2021)、 《阿迦》(2021)、《白蓮》(2021)、《環》(2021) 写真:Takeru Koroda
左から《冥華》(2021)、《阿迦》(2021)、《濁世に在る花》(2021)、 《阿迦》(2021)、《白蓮》(2021)、《環》(2021) 写真:Takeru Koroda
西久松友花さんは亀岡市出身。両親が日本画家だったこともあり、幼少期から美術に親しみながら育ちました。高校は美術系の学校に進学し日本画を学びましたが、絵だけではなくモノを作ることにも興味が湧き、大学では陶磁器を専攻します。「土に触れていると、手にしっくり来る感覚がありました」と、すぐに陶磁器の世界にのめり込んでいきました。
陶磁器は技術や知識、経験値がものを言う世界です。焼成中に起こる様々な変化、土の収縮や熱による歪み、釉薬の流れる方向、化学変化などを綿密に計算しなくてはいけません。加えて、窯の大きさを越えるサイズの作品は作れないなどの制約もあります。それでも、作品を焼成し窯から取り出す時の感動は、何にも代えがたい喜びがあると言います。窯の中はある種、人知の及ばない領域。時として自分の想像の範疇を超える作品が生まれてきます。
 アトリエにはナンバリングされた各種材料や、釉薬の発色や垂れ方を確認するための陶片などが所狭しと並べられ、日々素材を探求していることがわかります。
アトリエにはナンバリングされた各種材料や、釉薬の発色や垂れ方を確認するための陶片などが所狭しと並べられ、日々素材を探求していることがわかります。
大学入学以降、京都市を拠点としていたため亀岡で作品を制作、発表する機会はありませんでしたが、2020年に「かめおか霧の芸術祭」実行委員会から芸術祭で亀岡にまつわる作品を発表しないかとの誘いを受けます。「自分が生まれ育ったまちと向き合う良い機会になる」。そう考え依頼を快諾しました。
作品制作のために亀岡をリサーチしていく中で、芸術祭の展示会場となる亀岡市文化資料館が、元は亀岡市立女子技芸専門学校の校舎だったことを知りました。昔からよく知っている場所に、実はそんな由来があったなんて。文化資料館の入り口の脇には、技芸専門学校の生徒たちが針供養をするための針塚跡が今も残されています。そこから作品のアイデアが浮かびました。
針供養では、古くなった針を豆腐やこんにゃく、もちに刺して川に流したり、土に埋めたりします。それに倣って磁器土で四角い土台を作り、カラフルな刺繍糸を散りばめ、無数のまち針が刺さっているような表現を試みました。泥に浸した刺繍糸を窯で焼成するという特殊な技法を用いるなど、細部にまで西久松さんらしいこだわりが詰め込まれた作品になりました。
 《くよう》(2021)
《くよう》(2021)
「自分の故郷と向き合い、新たな作品が生まれたことは、自分の中ではとても大きな出来事でした。私という人間を形作っているのは、生まれ育った亀岡という土地。そんな自分の歴史が作品に生かされています」
単純に綺麗なもの、美しいものを作りたいだけじゃない。そうではなく、見た人たちに作品の文化的背景を感じてもらったり、共感したりしてもらいたい。「この形、知っている」「昔見たものに似ている」といった、人々の記憶の底に沈んでいる形を掬い上げるような、導き出すような作品を目指しています。
子どもの頃、よく父親とスケッチに出かけていたという西久松さん。画家である父親の画題が神社や自然だったこともあり、一緒に狛犬や樹木を描いていました。そういった亀岡での幼少期の経験、記憶の奥深くに眠っている様々なものが再び湧き出してきて、今の表現へと繋がっているのです。
 写真:Kaori Yamane
写真:Kaori Yamane
西久松友花
1992年京都府亀岡市生まれ。
2018年京都市立芸術大学大学院美術研究科工芸専攻陶磁器修了。
歴史のあるもの、現代まで継承された伝世品や土着の文化、宗教的象徴物などを、土という素材に置き換えて再構築、再解釈している。
取材日|2022年4月28日
取材・文責|宮下忠也(京都府地域アートマネージャー・南丹地域担当)
(記事執筆:宮下忠也(京都府地域アートマネージャー・南丹地域担当))