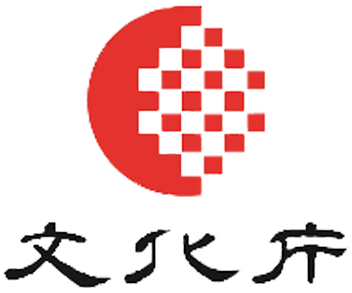山城地域|木津川市
本記事は、2021年度にWEBサイト【京都府地域文化創造促進事業】内「クリエイターズファイル」に掲載したアーカイブ記事です。
 鹿背山の花鳥風月を一望する水島家の敷地で。彫刻家・水島太郎さん
鹿背山の花鳥風月を一望する水島家の敷地で。彫刻家・水島太郎さん
京都府南部にある山城地域。かつてこの山城が「山背(やましろ)」と記された時代がありました。遡ることおよそ1,300年前、奈良時代に都が置かれた平城京から見ると奈良山の後ろにあることから、そう名付けられました。そして、この山城地域は奈良(平城京)との深い繋がりの中で文化を育み、歴史を重ねてきました。
そんな山城地域に、地域の歴史のように、奈良と深い関わりを持って作品を生み出す作家がいます。彫刻家の水島太郎さんは、お祖父さんの代から彫刻を営む一家に生まれました。祖父は木彫やブロンズ、乾漆の技法で仏像や母子像を彫った水島弘一さん(1907-82)、父は脱活乾漆技法を用いた弥勒菩薩をはじめ絵画や陶芸でもその才を発する水島石根(いわね)さん(1939-)です。
水島さん一家が代々暮らしてきたのは、鹿背山(かせやま)という山城内の京都府木津川市内にある地域で、平城京跡のすぐ北に位置する、古くからの里山の風情が漂う場所です。50年ほど前に祖父が開墾した水島家の敷地には、ギャラリーを併設したアトリエや窯があり、庭先にはごろんと彫刻作品がいくつも置かれ、ちょっとした彫刻のテーマパークのような雰囲気です。この場所で生まれ育った水島さんは、ごく自然に、気がついたら彫刻の道を歩いていたそうです。
 脱活乾漆技法で作られた『猫』
脱活乾漆技法で作られた『猫』
水島さんが主に手がけるのは、「脱活乾漆(だっかつかんしつ)技法」を用いた彫刻作品です。「だっかつかんしつ」。聞きなれない言葉ですが、「脱活」とは内部が空洞であることを意味し、「乾漆」は漆が乾燥し硬くなったことを表します。粘土で大まかな形を作り、その上に、漆と砥粉(とのこ)という砥石を切り出す際に生じた粉末を混ぜて塗り込んだ麻布を貼り付けて乾燥させます。その工程を繰り返し、乾き切ったところで、中から粘土を取り出し、残った外側が作品となります。興福寺の「阿修羅像」や東大寺法華堂の「不空羂索観音立像(ふくうけんさくかんのんりゅうぞう)」などもこの技法で作られています。この技法を用いるようになった背景を、水島さんが教えてくれました。
「この技法は天平時代の仏像彫刻に使われていましたが、漆は金と同じくらい高価であったことや扱いに手間がかかったので、この時代を最後に衰退していきます。それが第二次世界大戦の時に、(彫刻でよく用いられる)ブロンズなどが金属の供出で使えなくなり、それに代わるものがないかを父の芸大時代の先生が考えて、脱活乾漆技法を復活させました。それを父が手伝い、その後僕も手伝う中で、この技法を面白いなと思うようになりました」
 漆に砥粉と水を混ぜてパテ状にし、麻布に塗り込みます。この麻布を粘土で作った原型に貼り付けていきます。
漆に砥粉と水を混ぜてパテ状にし、麻布に塗り込みます。この麻布を粘土で作った原型に貼り付けていきます。
脱活乾漆技法を面白いと思う一方、水島さんは、かつてピカソやマティスらが暮らした、美術の“本場”であるフランスに興味を持ち、関西の私立大学でフランス文学を専攻しました。その後、自身もそのフランスに行きたいという希望を叶えて渡仏し、南仏ニース近郊の町で2年半を過ごします。縁あって画家マーク・エステル(1943-)の家に居候したこの期間は、雑用をこなす合間に自身の作品を制作するという、彫刻家としての礎を作っていく時間となったそうです。
「外国に行ったというのは、(自分の中で)大きかったですね。漆でやるというのは決めていたのですが、(渡仏時は)日本で100円ショップが流行り出した頃で、器とか漆のお盆を使わなくなり、プラスチック製の安いものが流通し始めていました。一方で、フランスは1000年以上前からあるアパルトマン(集合住宅)があったり、古いものを大切にする文化が残っていました。そんな中で、日本の伝統文化を使ってもう一度何かしたいと思うようになりました」
志を得て日本に戻った水島さんは、地元・鹿背山の作家たちとグループ展を開くなど精力的に制作活動を続け、自らの作風を確立していきます。今、そのアトリエには、脱活乾漆特有の温かみのある質感を特徴とする作品が並んでいます。仏像彫刻に触れて育った東洋のルーツと、フランスで体得した西洋のエッセンスが融合したような、不思議な魅力を発する生き物たちです。
 作品が並ぶギャラリー兼アトリエ
作品が並ぶギャラリー兼アトリエ
祖父、父、マーク・エステル。偉大な芸術家たちに学んだ水島さんが、今、一番影響を受けているのは奈良・東大寺の修二会(しゅにえ)です。修二会は「お水取り」や「お松明」とも呼ばれ、人々が日常に犯す様々な過ちを僧侶たちが懺悔するという法要行事で、毎年3月1日から2週に渡って行われます。
「(修二会は)昨年1270回目だったんですが、これまで一度も途絶えたことがありません。そこに15、6年前から参加していて、お坊さんたちと一緒に二月堂に1ヶ月ほど篭って生活します。期間中、お坊さんたちは外に出られないので、彼らの料理を作ったり身の回りの世話をするのが主な役割です。その中でも特に大きな仕事は、松明を作り、仏事を行うためお堂に上がるお坊さんたちの足元を照らして歩くことです」
 修二会で松明を持つ水島さん(左列の二人目)
修二会で松明を持つ水島さん(左列の二人目)
本来の仕事である彫刻とは関係がないようにも思えますが、水島さんは修二会に参加する理由を次のように語ります。
「それが関係してるんです。精神的な面ですけど、感覚が研ぎ澄まされます。寒い時期なのにストーブもなくて炭で暖を取ったり、毎年二人部屋なんですけど、布団が重なって足が当たるみたいな狭いところで2週間過ごします。日常とは全く違うところに行くんですね。そこでの生活から、すごいインスピレーションが入ってきます。フランスから帰ってきた頃に誘ってもらい、どんなことをするのか全く知らずに行ったら、ハマったというか魅了されました」
 取材の合間に父・石根さんも時々出入りして話を聞かせてくれました。常に穏やかな水島さん。
取材の合間に父・石根さんも時々出入りして話を聞かせてくれました。常に穏やかな水島さん。
世の中が新型コロナウィルス感染症の流行で一変した頃、『手のひらに桃を』という独自の活動を始めました(現在は終了)。その内容は手のひらサイズの「桃」の彫刻を作り、会う人全員に配るというものです。3月2日生まれの水島さんは、もし1日遅れて3月3日に生まれていたら「桃太郎」と名付けられる予定だったことから、モチーフに選んだ「桃」は水島さんにとって思い入れのあるアイテムなのだそう。そんな「桃」を、水島さんは自身の殻(脱活乾漆技法の工程で最後に残る殻)に見立てました。そして、素材である漆と麻に触れた人たちに日本の伝統文化に関心を持ってもらうこと、邪気を払う神聖な果物として「古事記」にも登場する「桃」をコロナ禍のお守りにして手元に置いてもらうこと。そんな思いが込められ、これまで500個以上の「桃」が様々な人の手に渡っていきました。
 水島さんのSNS投稿サイトには「桃」を手にした様々な人たちの写真が投稿されています。(写真提供:水島太郎さん)
水島さんのSNS投稿サイトには「桃」を手にした様々な人たちの写真が投稿されています。(写真提供:水島太郎さん)
『手のひらに桃を』の活動は、共感したアート関連のプロデューサーとの新たな作品制作の機会を生み、中国の景徳鎮で金箔に包まれた新たな「桃」が誕生しました。コロナ禍という非日常が日常の風景となる中、水島さんにしか生み出せない唯一無二の世界観をまとう作品は、これからも私たちの日常に一服の安らぎを与えてくれることでしょう。
 中国の磁器の産地・景徳鎮で作られた金の「桃」
中国の磁器の産地・景徳鎮で作られた金の「桃」
取材日|2022年1月11日、18日
取材・文責|西尾晶子(京都府地域アートマネージャー・山城地域担当)
写真撮影|馬渕拓真

水島太郎
京都府木津川市出身。祖父・弘一、父・石根より三代目彫刻家として乾漆技法などを継承。2002年、関西大学フランス語学科卒業後、渡仏。南仏ニース近郊のエズに住み、画家マーク・エステルのアトリエにて制作。2005年頃より東大寺修二会に毎年参籠。現代彫刻で脱活乾漆造の新たな展開を目指す。
(記事執筆:西尾晶子(京都府地域アートマネージャー・山城地域担当))